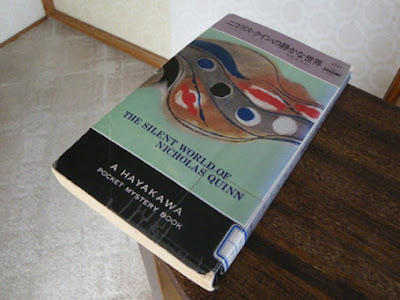時代を語る車達 ⑤
 出かけた先で撮影した車の写真に、個人の感想的な解説を付けたシリーズです。 あくまで、私個人の意見なので、自分が好きな車を貶されたからと言って、怒髪衝天するに及びません。 ちなみに、私は、ブログだから、こういう事を書いているのであって、現実世界では、面と向かって、人様の車を、ああだこうだ、批評したりしません。 普通、乗せてもらったら、いい所を探して、誉めます。
出かけた先で撮影した車の写真に、個人の感想的な解説を付けたシリーズです。 あくまで、私個人の意見なので、自分が好きな車を貶されたからと言って、怒髪衝天するに及びません。 ちなみに、私は、ブログだから、こういう事を書いているのであって、現実世界では、面と向かって、人様の車を、ああだこうだ、批評したりしません。 普通、乗せてもらったら、いい所を探して、誉めます。 そういえば、人の車に乗せてもらっていながら、感謝するどころか、乗せてもらっている負い目を感じるのが嫌で、わざと、横柄な態度をとるばかりでなく、ぞんざいに、車のあちこちを弄り回し、貶せる所をほじくり返して、貶しまくるという、苛烈な馬鹿が、決して少なくない割合で存在します。
もし、相手が、親しい人間なら、やんわりと、「そういう事は、言うもんじゃない。 自分が同じ事をされたら、嫌だろう」と諭してやるべきですな。 「冗談だよ、冗談!」などと、その場では、笑ってごまかされてしまうかも知れませんが、こちらの言った事が、じわりと効いて、恐らく、二度としなくなるでしょう。 遅れ馳せながら、常識の片鱗を知って、ほんのちょっと、大人になれたわけだ。
さして親しくない相手なら、車を停め、引きずり下ろして、「この馬鹿が。 他人の車に乗ろうなんて、二度と思うな」と言い放ち、そこへ捨てて行くべきでしょう。 そして、職場でも学校でも、共通の知人がいる場で、「あいつには、こういう事をされた」と、先手を打って喋りまくるのが良いと思います。 そういう馬鹿は、自分のどこが悪いのか分からなくて、他の人間に対しても、同じ事をするので、いずれ、評判が悪くなって、誰も相手にしなくなります。
9代目カローラ。 2000年から、2006年まで、生産・販売されていた型です。 実は私、この車を工場で作っていました。 ほとんど、記憶がないのは、やっていた仕事が、タイヤ取付で、他の車種も、やる作業は同じだったからです。 ちなみに、私が勤めていた工場だけではなく、他の工場でも、同じ車種を生産していました。
自分で作っていた事とは関係なく、このカローラのデザインはいいと思います。 パッケージングに、全く無駄を感じさせない一方で、特徴もあって、良く纏まっています。 惜しむらく、この型が現行だった頃には、もう、セダン人気が落ち込みきっていて、カローラといえども、かつてのような大量販売など、望むべくもありませんでした。
2000年代初頭の2時間サスペンスに、覆面パトカー役で、この車が登場すると、「ああ、いいなあ」と思うのですが、それは、ノスタルジーではなく、逆に、このデザインが、古さを感じさせないからでしょう。 下手に、カッコつけようとしていない分、この後の10代目よりも、成熟感は高いと思います。 この型に、今でも乗っている方々には、無理してでも、乗り続けていただきたいもの。
≪写真右端≫
ダイハツの、ミラ・ココア。 2009年から、2018年3月まで、生産販売されていた車。 モデル・チェンジはせずに、一代限りで終わってしまったようです。 たぶん、「キャスト」が、後継車という事になるのでしょうが、ココアは、完全に女性向けなので、ほとんどのユーザーは、ココアの後に、キャストに乗り換える事はしないと思います。
デザインは、「女性向けレトロ」とでも言うべきコンセプトに、ピッタリ合っていて、大変良いです。 「ルノー4」のパクリと分かっていても、貶す気にならないから、大した完成度。 ほぼ同じコンセプトの、スズキ・ラパンを横目に見て企画されたものだと思いますが、ラパンの、初代(2002年-2008年)には、僅かながら勝り、2代目(2008年-2015年)には、普通に勝ち、3代目(2015年-)には、圧勝というところ。
ホイール・カバーのデザインが凝っていて、それがまた、質感を盛り上げるのに、大きな役割を果たしています。 シルバー単色のホイール・カバーを付けた車と並べて見ると、段違いに良い。 大抵のアルミ・ホイール車と比べても、こちらの方が勝っていると思います。 もっとも、ツートンのホイール・カバー、もしくは、アルミ・ホイールというのは、過去の他の車でも例があり、ココアの発明というわけではないようですが。
この車を見るたびに、女に生まれなかった事が、悔しくて悔しくて、地団駄踏む思いです。 ちなみに、男が、これに乗るのは、かなり、無理があります。 その人のイメージが悪くなるのを心配しているのではなく、車のイメージを悪くしてしまうので、控えてもらいたいもの。
≪写真中央≫
ダイハツの、初代ミラ・イース。 2011年から、2017年まで、生産・販売されていました。 ハイブリッドではないのに、ハイブリッド並みの燃費を実現していた、稀有な車です。 しかも、70万円台と、驚くほど安かったのだから、凄い企画もあったもの。 ハイブリッド車は、元が取れない、マヤカシ技術だと思いますが、イースだけは、本当の低燃費車と言えます。
デザインもいいと思うんですが、リヤコンに、LED球を並べていたのが気に入らなくて、「あれさえ、変われば、買うのになあ」などと、具体的に買う予定もないくせに、思っていました。 結局、最後まで、変わりませんでしたけど。
この写真の車は、前期型ですが、後期型になると、フロント・バンパーの下の方のデザインが変わり、フォグ・ランプのダミーのような整形になってしまいました。 あんなのにするくらいなら、前期型のままの方が、ずっと良かったのに。
≪写真左端≫
ダイハツの、5代目ムーヴ。 2010年から、2014年まで生産・販売されていた型。 これの前の、4代目が、歴代ムーヴの中では、最も、デザインが纏まっていたと思うのですが、5代目は、ちょっと、崩した感じですな。 恥ずかしながら、私は、前側だけ、パッと見たのでは、4代目と5代目の区別が付きません。 横に回って、プレス・ラインの位置を見て、ようやく分かるという程度の認識です。
ムーヴだけでなく、トール・ワゴン全てに言える事ですが、シートが高いので、もし、老人を乗せるのであれば、避けた方がいいです。 アルトやイースなど、普通の軽なら、お尻を先に乗せて、後から脚を入れるという順序で、体に負担をかけずに乗り込めるのですが、トール・ワゴンとなると、片足を先に入れ、手を、ドアやシート座面に踏ん張りながら、体を浮かせて、尻を乗せるという順になり、若い人間なら、何でもない事ですが、高齢者には、非常にきつい、もしくは、全くできない、乗り込み方になってしまいます。
「年寄りを乗せるのだから、天井が高い方が、頭がぶつからなくて、いいだろう」とは、誰でも考える事ですが、乗り方を細かく分析すると、トール・ワゴンは、高齢者向きではないんですな。 ワン・ボックスなら、尚の事で、体が利かなくなっている人に、高いシートに這い上がれというのは、限りなく、拷問に近いです。
≪写真上≫
逆光で、分かり難くて、申し訳ないのですが、向かって左側の車は、ダイハツの、エッセです。 2005年から、2011年まで、生産・販売されていた車。 一代限りで、終わったようです。 比較的、廉価で、ダイハツ車の入門モデルという位置づけだったとの事。
ミラ・ココアの時に、「ルノー4のパクリ」と書きましたが、このエッセは、それ以上のパクリ度で、「ルノー5のパクリ」だと思います。 最初に見た時に、「ややっ! これ、いいのかいな?」と、他人事ながら、心配になりましたから。 ルノー4とココアの方は、指摘されなければ気づかない人も多いと思いますが、ルノー5とエッセは、両方を見た事がある人なら、誰でも気づくレベルの似方です。 似せ方というべきか。
後ろ姿は、違うように見えるかもしれませんが、ルノー5には、ミッド・シップに改造した、ターボ車がありまして、そちらも有名でした。 そのルノー5・ターボの、特徴的なオーバー・フェンダーを、エッセでは、リア・バンパーのデザインで写しているように見えます。 とことん、ルノー5のイメージを戴いているわけですな。
「オマージュ」という言い方は、映像作品では良く使われますが、製品デザインの場合も、使えるんですかね? 10年くらい前、中国の新興自動車メーカーの幾つかが、日本車そっくりの車を出していた時、日本では、「パクリ! パクリ!」とボロクソに扱き下ろしていたのですが、そういう人達が、ちょうど、その頃に売られていたエッセを、どういう目で見ていたのか、訊いてみたいです。 「オマージュ」と言いますかね? まさか、「ルノーの許可を取っていたに違いない」なんて、言わないだろうね?
あまりにも、ルノー5に似過ぎているので、デザインに関しては、評価のしようがありません。 大抵の人は、エッセを見ると、「いいデザインだ」と感じると思うのですが、それは、エッセのデザインが優れているのではなく、モデルになった、ルノー5のデザインが優れているという事なんですな。
とはいえ、エッセを買っていたのは、恐らく、世代的にも、性別的にも、ルノー5を全く知らない人達だったと思うので、「似ている」と指摘しても、「それが、どうした?」と言われるのがオチだと思います。
≪写真下≫
右側の黒い車は、ますます、写真が悪くて、恐縮ですが、日産で販売されていた、3代目モコです。 期間は、2011年から、2016年まで。 生産は、スズキで、3代目MRワゴンの相手先ブランド供給製品。 スズキより日産の方が販売力が強いので、かなりの数が売れたものと思われます。
デザイン的には、これも、いい評価はできません。 後ろ姿には、個性があって、私が好きというわけではないものの、ああいう形を好む人もいると思のですが、前がねえ・・・。 元になった、3代目MRワゴンの方は、ヘッド・ライトの形に特徴があって、「困ったナー」という感じの目つきが面白かったのに、このモコでは、オーソドックスな形に変えられて、後ろ姿とのバランスが崩れてしまっています。
そもそも、日産も、なんで、ワゴンRの4代目・5代目を、供給して貰わなかったんですかねえ? そうしていれば、馬鹿売れしたと思うのですが。 同じスズキが作った、トール・ワゴンでも、大違いです。 モコは、3代目で終わり、その後継車は、日産と三菱が共同開発した、デイズになるのですが、3代目モコに比べると、デイズは、劇的に良くなった感じがしますねえ。
今回は、以上、5台まで。
このシリーズ、写真の在庫は、まだ十数枚ありますが、今現在は、増えていません。 なかなか、私が食いつきたくなるような、古い車がなくてねえ。 90年代の車は、まだ、見かけますが、80年代となると、もう、ほとんど、姿を見ませんなあ。 86とか、2代目ソアラとか、その筋の人達が好みそうな車なら、残っていますが、私は、そういう車に、まるっきり興味がないのです。
ネットの中古車サイトで、古い軽を探すと、アルト・ワークスとか、ミラXXとか、ハイ・パワー・スポーツ・バージョンの残存率が高いのが分かりますが、「車好き」=「スポーツ走行好き」という図式には、否定し難いものがあります。 残念ながら、普通の車に乗っている人達は、どんどん、新しいのに買い換えて、古い車は、廃車にされてしまうのでしょう。